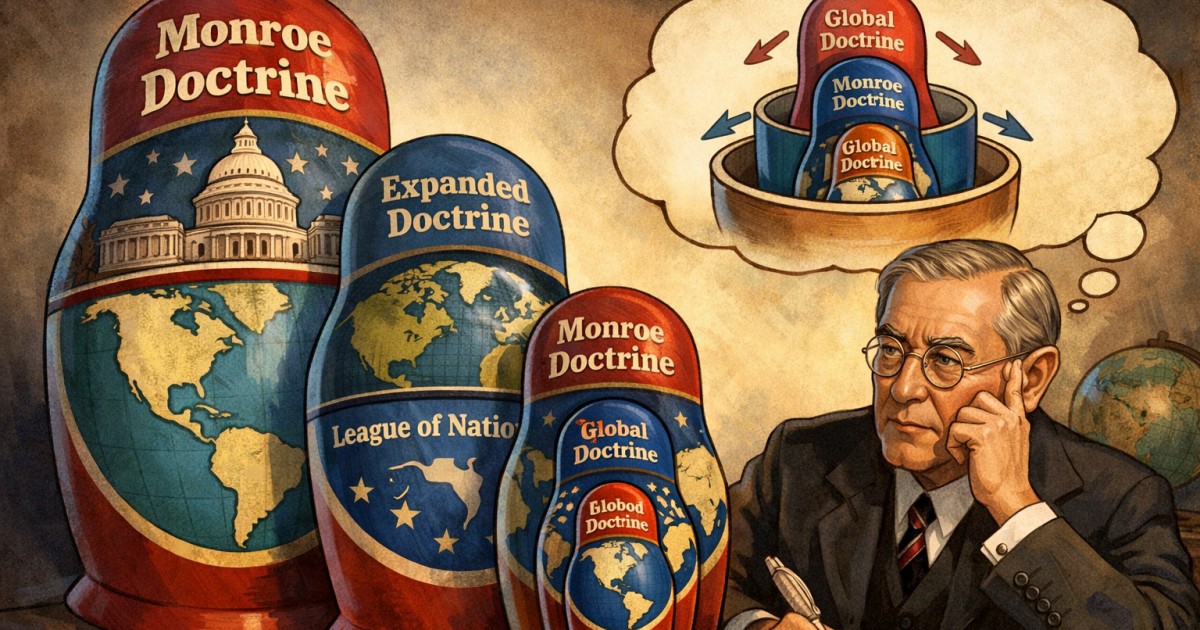日曜討論における岩下明裕教授の発言
岩下教授は、番組出演にあたって前日夜に松里公孝・東京大学教授と電話で会話をして意見交換をした、と番組中に述べた。正直、松里教授の実名を出したところで、隣の隣の席にいた私は驚きを禁じ得なかった。
松里教授は、東京大学法学部でロシア政治の講座を担当している、この分野での日本の第一人者である。その国際的で重厚な業績は、同業者が深く認めるものである。モスクワ大学での在外研究歴はもちろん、近年のドンバス戦争勃発後の時期に、ウクライナ東部に入ってドネツク/ルハンスク人民共和国当局の要人などに対しても聞き取り調査をしているなど、旧ソ連圏での豊富な人脈にも基づく研究活動も素晴らしい。
ところがこの濃厚な研究歴のゆえに、ロシアのウクライナ全面侵略後には、「ウクライナは勝たなければならない」主義の方々の不当な「親露派潰し」攻撃の標的になってきた。松里教授は、「親露派」の思想に取りつかれている、という言説が、「ウクライナ応援団」界隈では定説となっており、SNSなどで松里教授の人格攻撃の言葉があふれかえっていた時もあった。その結果、22年の全面侵攻直後の時期には松里教授の見解も聞いたりもしていた日本のメディアは、その後はピタリと松里教授の意見を聞くのをやめてしまった。
私に言わせれば、日本の言論界の閉塞状況の象徴と言える事態であり、日本の知的財産の損失と言ってもいい事態であった。
私自身は、自分の属する大学の研究会に松里教授をお招きして議論させていただき、夕食の席も含めて広範なご意見をいただいたこともある。大変に有益であった。ウクライナ人研究者4名とやっている共同研究にも松里教授をお呼びしようかと考えたこともあるが、これはウクライナ研究者側の意見を聞いた際に、「松里教授は有名すぎる、ウクライナの大学ではモスクワ留学歴を持っているだけでもう在籍できないような事態だ、いっしょに研究会をやった記録は作れない」と言われたので、あきらめた。その逸話を松里教授ご本人にも伝えたところ「戦時下の国の学術活動に大きな制約があることは理解する」と寛大なご発言をいただいた。
その松里教授と会話をして、岩下教授は、起こり得るウクライナの選挙の見込みについて語り始めた。