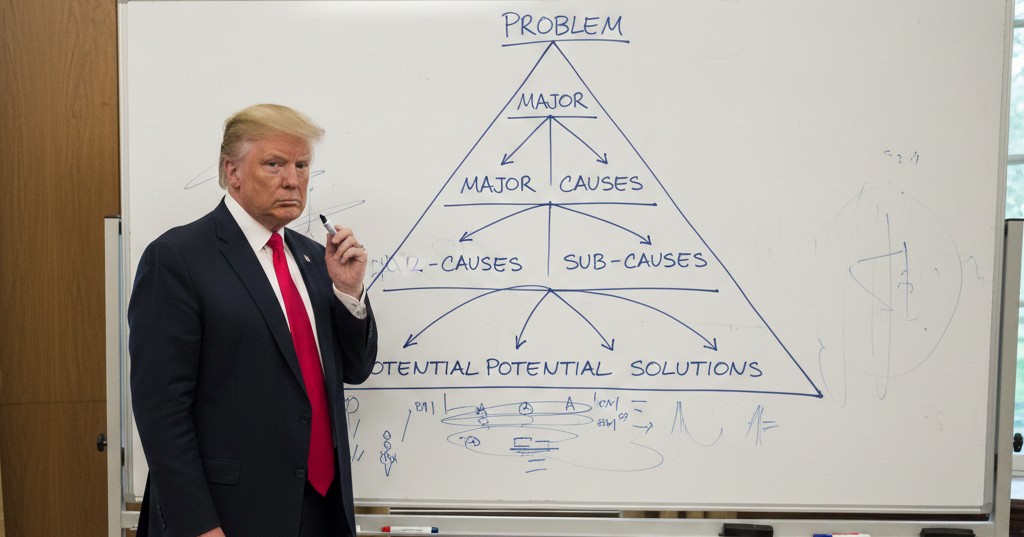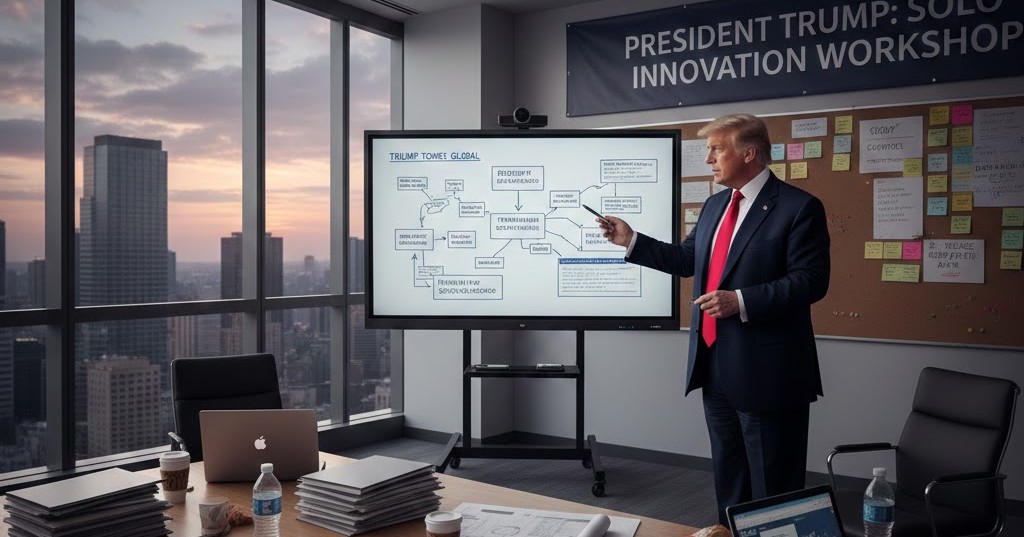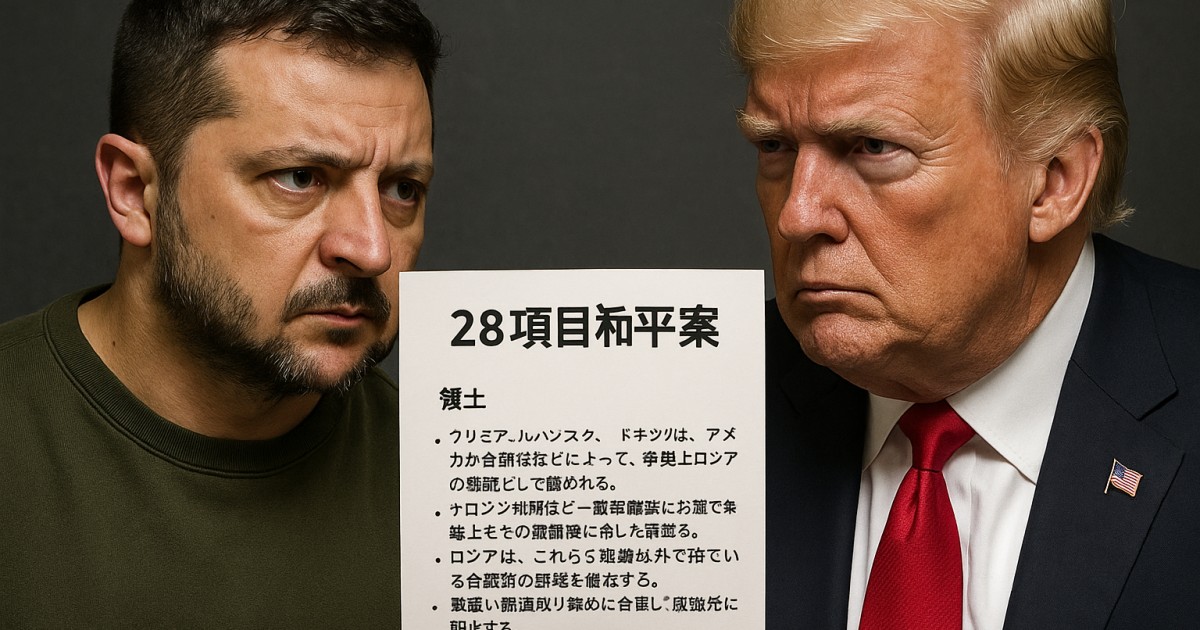米国の「クリミア宣言」の放棄の可能性と「スティムソン・ドクトリン」の帰趨
クリミア問題が内包する三つの問題領域
トランプ政権が、ロシア・ウクライナ戦争の調停努力の一環として、ロシアのクリミア併合を承認することを検討していることが話題だ。これは当初はリーク記事としてメディアに流れてきたもので、まだ公式説明というものはなされていない。ただ、トランプ大統領やゼレンスキー大統領の発言内容を見ると、ほぼ確定的なことであると思われる。
このことについて巷では、トランプ大統領の「力による現状変更を認める」蛮行として、非難の対象となっている。2014年クリミア併合は、諸国の大多数が承認しておらず、国際法学者の大多数が認められない併合と考えていることが明らかであるため、こうした世論の動向には理由がある。ただかなり感情的に捉えられている傾向も強く、問題が正確には理解されていない、と感じざるを得ない場面に出会うことも少なくない。
非常に大きな問題であるだけに、感情的なトランプ大統領人格非難だけに特化しただけの理解にとどめてしまうと、後々、リスクが生じかねない。むしろ非欧州地域の諸国の人々は、より中立的な立場から、この問題を冷静かつ大局的な視点からとらえている。感情論だけを先行させると、非欧米地域の諸国の人々と、知的な会話ができなくなる。
クリミアの問題を捉えるには、現在進行形の停戦交渉の文脈での理解、クリミアが持つ複雑な歴史からの理解、そしてアメリカの外交政策におけるスティムソン宣言の伝統の理解、という三つの位相に分けていくことが、まずは肝要と思われる。いずれも大きな問題であるが、それぞれの基本的論点を整理する作業を行ってみたい。
停戦交渉における米国によるクリミア併合承認の意味
ゼレンスキー大統領がウクライナはクリミア併合を認めないと発言しているのは停戦交渉に阻害的だ、と批判する内容のSNSポストを、トランプ大統領が投稿したことが、話題となった。そこにおいてトランプ大統領は、「誰もウクライナにクリミア併合を承認しろとは言っていない」と書いた。これはどうやら正しいようである。
承認を検討しているのは、あくまでもアメリカである。アメリカ合衆国は一つの主権国家として、ある外国領土がどの国家に属しているのかを判断することができる。自国の判断をウクライナのような他の主権国家も同調するように強要した場合には、国際法違反の威嚇にあたるが、アメリカが独自の判断でクリミアはロシアに属していると判断すること自体は、可能である。
国際法は、一般原則としては、諸国の同意原則に依拠している。ある領土の帰属が、複数の国家によって争われている場合、第三国がどちらかの国を支持する立場をとりうることは、当然起こりうることとして認められる。
基本的には、トランプ大統領は、停戦交渉を成立させるための「取引」材料として、自国によるクリミア併合の承認というカードをちらつかせている。これはこれで語るべき内容が多々あるが、これについてはすでに4月23日「垣間見えたアメリカの調停姿勢と欧州安全保障のリスク要素」記事でかなり。
クリミアの歴史の意味
クリミアは黒海の制海権に大きな影響を与える戦略的要衝である。19世紀のクリミア戦争は、大規模かつ国際政治に大きな影響を放った戦争であった。このときは、イギリス・オスマン帝国側が、ロシア帝国に勝利し、ロシアの南下政策を封じ込めた。ただしロシアがクリミア半島を放棄したわけではない。また黒海の南西の沿岸地域であるバルカン半島は、クリミア戦争以降に大国間の勢力争いが和らぐどころか一層激化していき、遂には第一次世界大戦の直接要因となった。
言うまでもなく当時はウクライナという国は存在しておらず、今日につながる領有権の問題は発生しようがなかった。ウクライナは、第一次世界大戦(ロシア革命)後に動乱の中で独立を宣言するが、すぐにソ連に吸収されてしまった。そこでクリミアは、ソ連では、ロシア共和国に属していた。ただしウクライナ育ちとして知られるフルシチョフが書記長に就任した後の1954年に、フルシチョフの指導で、クリミアのウクライナ共和国への移管が行われた。そして1991年にソ連が崩壊した際、共和国の境界線が引き直されることはなかったので、クリミアは独立したウクライナの領土となった。
この経緯に多くのロシア人が不満を持ち、2014年にウクライナでマイダン革命が起こった際、首都キーウでの動きにクリミアが取り残されているのを見て、ロシアが事実上の侵攻をして確保した。手続き的にはクリミア及びセヴァストポリ特別市がマイダン革命後のウクライナ政権の統治から離れて独立を宣言した後、ロシアへの帰属を求める住民投票を行った、という措置が取られることになった。この手続きの正当性について、当時プーチン大統領は、繰り返し「コソボの先例」を持ち出して、擁護した。https://gendai.media/articles/-/41158?imp=0
コソボは、1999年のNATOの軍事介入後に、実態としてセルビア共和国の統治から離れ、その後2008年に独立宣言を行った。欧米諸国や日本はコソボを国家承認しているが、現在でも世界の約半数の諸国は、コソボを国家承認していない。
コソボとクリミアの間には、無視しえない重大な相違があり、単純な比較は許されない。しかしプーチン大統領が徹底して「コソボの先例」を主張し、コソボもまた国際法上の地位は完全には明確ではないという点で、クリミアの併合の歴史に「グレイゾーン」にふれてくるような要素があることは完全には否定しがたいところはある。そしてそれは巨視的な地政学的見取り図とも大きく関わる。(拙著『国際紛争を読み解く五つの視座』[講談社、2015年]第三章参照)
スティムソン主義の帰趨
ゼレンスキー大統領は、SNSを通じて、アメリカが2018年に当時のポンペオ国務長官名で武力による領土変更を認めない「クリミア宣言」を行っていた事実について、言及した。https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3985332-zerenshiki-yu-da-tong-lingnianni-mi-guoga-fa-chushitakurimia-xuan-yanwo-huan-qi.html
この2018年「クリミア宣言」は、バルト三国のソ連併合を認めなかった1940年「ウェルズ宣言」を参照していた。アメリカは、冷戦時代を通じても、「ウェルズ宣言」を維持して、バルト三国のソ連による併合を認めない立場を貫いた。
実はこうした「不承認主義」の伝統は、1932年「スティムソン・ドクトリン」の伝統に由来する。当時、大日本帝国が、自作自演で満州事変を引き起こし、「満州国」の樹立を宣言したところであった。満州国は日本の傀儡政府に過ぎず、アメリカは武力による一方的な領土変更を認めない、という立場を宣言したのが、当時のアメリカのヘンリー・スティムソン国務長官であった。1919年国際連盟規約や1928年不戦条約によって、今日にまで連なる武力行使禁止の原則は、すでに国際法に導入されていた。しかしまだ定着していたとまでは言えなかった。そこで原則に忠実に武力によって作られた現実は決して承認しない、という立場を明らかにしたスティムソン国務長官の宣言が、非常に重要な先例になるものとして、有名になったのである。
現在、まだトランプ政権がロシアによるクリミア併合を承認するにあたり、2014年に立ち返って併合の合法性を認める立場をとるのか(これまでの立場の撤回)、あるいは2025年の現実を見てクリミアがロシアに属していると判断するのかは、まだわかっていない。
実は法的に大きな行為になるのは、後者のほうである。違法行為から合法的な事実は生まれないと考えるのが現代国際法の原則だ。もし継続的な実効支配の現実が、領土の国家の帰属に影響する主張を行うとなると、19世紀国際法に立ち返るような論理構成を正当化する必要が出てくる。これは大変な出来事である。
クリミア併合と、その他のウクライナ東部4州を切り分けるのは、2022年の全面侵攻の前と後の現実の間に一線を引いて区別しようとする意図の表れに見える。したがってトランプ政権は、2014年に立ち返って、クリミアのロシアによる併合を認める立場をとるのではないかと推察される。ただし、前者の立場をとる場合でも、結果的に1932年「スティムソン・ドクトリン」の伝統を覆す意味を持つことになり、アメリカ外交政策の伝統において、大きな出来事となる。
この『The Letter』においても、これまで「モンロー・ドクトリン」や「アメリカン・システム」といった19世紀アメリカ外交の概念を用いて、トランプ政権の傾向を捉える分析を行ってきた。「1932年スティムソン・ドクトリンからの離脱」も、やはりトランプ政権の19世紀への回帰の傾向の証左として捉えておかざるをえないだろう。
すでに登録済みの方は こちら