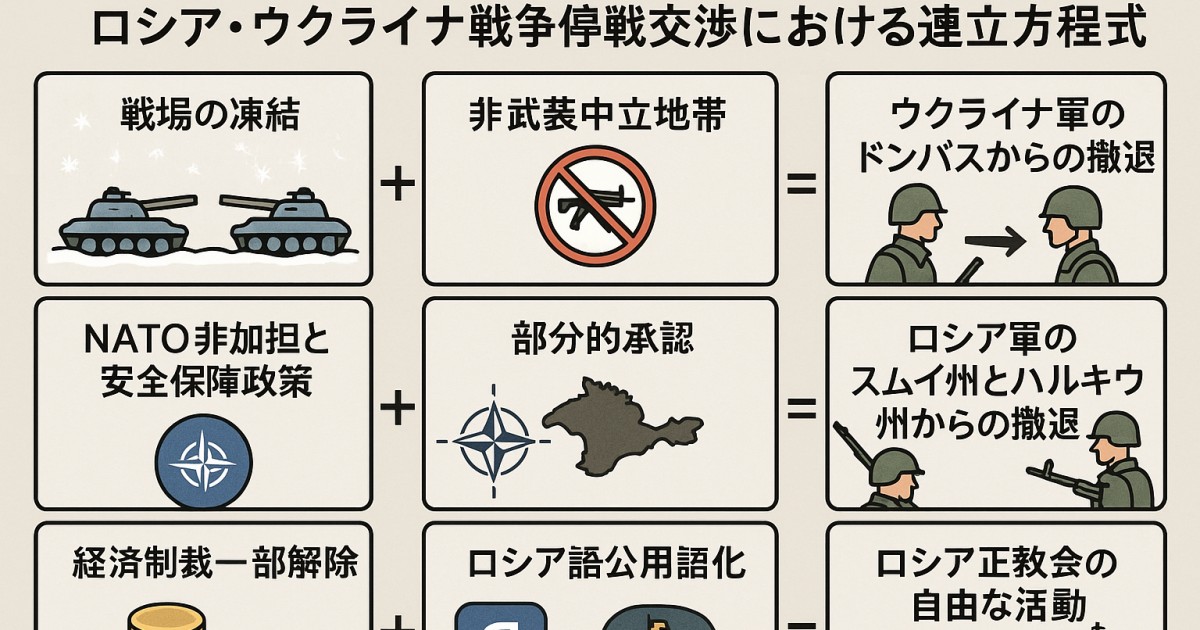「トランプ関税」問題の構造的な事情を見る
「トランプ関税」の背景にある本質的問題
過去3カ月弱の間、トランプ大統領が起点となった国際ニュースが多々生まれてきている。現在進行形の大問題は「トランプ関税」問題だが、これは現在では一騎打ちの形の「米中貿易戦争」に転換してきている。
現代世界の二大超大国の激突だ。今後の国際社会の動向にも、極めて大きな影響を持つだろう。展開次第では、かなり大きな影響が出てくる。大きなリスクも存在している。しかし相互に強みと弱みを持つ。どのような展開になるか、予測が難しいところがある。
第三者の立場にある日本は、あるいは漁夫の利を得る楽観的なシナリオもありうる。その一方、どちらかの、あるいは双方の巨像の崩落に巻き込まれて、混乱していく悲観的なシナリオの可能性もありうるだろう。
事態は流動的だ。日々の動きを正確に捉えておくことは必要だ。しかし、長期的な視点で状況をとらえ、国益を確保していく態度も同時に必要になっている。問題の本質は、アメリカの貿易赤字と財政赤字という簡単には解消できず、バイデン政権時代にむしろ深刻に悪化していた、構造的な問題にある。
残念ながら、毎時間の株式市場の動きに一喜一憂しながら、非常に短期的な視点で状況を追いかけている人は、相当な数で存在している。もちろんそれも重要だ。だが同時に、長期的あるいは構造的な視点からの事態を把握する姿勢も、持っておくべきだ。
トランプ大統領を理解する努力
そもそも問題を、トランプ大統領の個人的な性癖だけに還元してしまう見方が強すぎる。あたかもトランプ大統領が異星人(エイリアン)であるかのように際立って特殊な人物だと思い込みすぎると、状況分析も、トランプ大統領に対する感情的な思いだけに左右されてしまうようになる。
日本政府は、5万円の給付金を全国民に配る、という、意表を突いた対応策を検討しているという。アメリカの高関税率という事象への対応としては、理解に苦しむ対応策である。トランプ大統領の登場を異星人の襲来のように捉えてしまい、その結果、自然災害や感染症への対策と同じような対策しか思いつかなくなってしまっているのではないか、と危惧せざるを得ない。これは理解に苦しむというよりも、非常に大きな危険を感じさせる兆候だと言わざるを得ない。
すでに私自身は、トランプ大統領の就任以来、「モンロー・ドクトリン」や「アメリカン・システム」といったトランプ大統領が敬慕する19世紀アメリカの政治経済思想の概念を参照しながら、トランプ大統領の思想の基盤を分析しようとしてきている。トランプ大統領を、単なる異星人として捉えることなく、分析していくためである。
より直近の政策課題に対応した問題意識としては、史上最高規模にまで膨れ上がっている貿易赤字のみならず、財政赤字について、トランプ大統領は懸念を持っている。このこと自体は、間違った態度であるとは言えない。
ただもちろん確かに、思い切った高率関税を世界の全ての諸国に対して導入する、といった政策は、貿易赤字と財政赤字に懸念を持っている、といったことだけでは、完全には説明されえない。またトランプ政権は、公約として、近く大型減税を導入する予定だ。財政赤字削減の努力を減税実施の前に行っているつもりであるわけだが、これについても、冒険的すぎる政策だと感じる方が多いのは、当然ではあるだろう。そもそも21世紀に、19世紀のアメリカをモデルにした政策を取り入れるという発想そのものが、多くの人々にとって、破綻したものだろう。
だがそれにしても、トランプ大統領なりに、ある種の一貫した問題意識を持って、政策的な対応しようと苦闘はしている。それは、極めて巨大で構造的な性格を持つ問題だ。財政赤字に苦しむアメリカのもがき、それが今起こっていることの本質だ。
深刻さを増すアメリカの財政赤字
アメリカの財政赤字は、累積で2024年度に35兆ドルで、対GDP比で124%の水準に達している。史上最高水準である。2024年度のアメリカの貿易赤字は、1兆2117億ドルで、過去最大だった。社会の内実を見れば、貧富の格差や地域的な分裂が激しく、製造業の衰退による産業空洞化が深刻だ。果たしてこの社会が持続可能なのかどうかは、ある種の社会実験を通じて初めて結論づけられることだ。現時点では、わからない。
米中の貿易戦争でも明らかになるところだが、アメリカは中国の小物定額商品だけを買っているわけではない。電子機器や防衛装備品の部品などで、中国のレアアースや生産物に依存しているところがある。また中国が、大量の米国国債を保有していることにも、不気味な含意がある。国債が暴落したら、アメリカの国家としての存在が、大きな危機に陥る。
だが、そうであるがゆえに、アメリカは、デカップリング(切り離し)を行いたいわけである。長期的な視点に立って、アメリカ国内の産業社会構造を作り替える布石を打つ試みである。しかし理由があって依存しているわけなので、デカップリングは痛みを伴う。そもそも成功するかどうか、わからない。負担が大きすぎて、あるいは中国の敵対的な政策が功を奏して、アメリカの側に大きな危機が訪れる恐れもある。
名目GDPでアメリカのGDPは30兆3371億ドルで、2位の中国の19兆5348億ドルの1.55倍だが、購買力平価GDPでは1位が中国の34兆6601億ドルで、2位のアメリカの27兆7207億ドルの1.25倍ある。2024年のアメリカの経済成長率は2.7%だったが、中国の成長率は5%だった。アメリカは3.3億人の人口を持つが、中国は14億人だ。現時点で勢力は拮抗しており、しかも時がたてばたつほど、成長率が高く、人口が多い中国のほうが相対的な勢力を伸ばすのは必至である。
唯一の超大国アメリカからの脱皮
アメリカはすでに現時点で唯一の超大国とは言えず、将来にかけてますます複数の大国の一つとしての地位に甘んじていくことになる。インドのGDPは、2050年までにはアメリカを凌駕すると言われている(購買力平価GDPではもっと早く抜かすだろう)。2050年のGDPランクは1位中国、2位インド、3位米国、4位インドネシア、5位ブラジル、6位ロシア、7位メキシコといった具合に並んでいくのではないか、と予想されている。
アメリカにとっては、人口14億で急速な経済成長を遂げている中国やインドとしのぎを削る争いを繰り広げる。世界最高の超大国の立場から、複数の大国の一つに転換していくのは、簡単なことではない。しかも、あるいはもしも貿易赤字・財政赤字を悪化させ続けて破綻すれば、遂にアメリカも世界有数の大国としての立場も明け渡さなければならないかもしれない。
突き詰めれば、大胆過ぎるように見えるトランプ大統領の政策も、アメリカが大国の一つとして生き残るために必死で行っていることである。アメリカの地位の相対的な低下が必至であるとしても、なおアメリカの財政再建と経済成長率の維持は、世界有数の大国として存在し続けるためには、必須の条件だろう。少なくとも今のまま漫然と空前の規模の財政赤字の拡大を放置していても良いとは思えない。
トランプ大統領の個々の政策の短期的な効果についてどのような評価をするかにかかわらず、アメリカが置かれている立場を長期的視点から理解しておくことは、極めて重要になる。おそらくはアメリカと関税交渉をする際にも、重要になってくるだろう。
実はトランプ政権は、個々の国々との関税交渉を、独自に進めながら成功させたいと考えている。ベッセント財務長官は、日本との交渉を優先させると語っている。日本とアメリカの間には、1980年代のプラザ合意に始まり、一連の構造調整をめぐる交渉などを行ってきた歴史がある。
日本としては、短期的な視野にとらわれてトランプ政権を批判するような態度を避け、長期的な視点に立って共通利益を見出そうとする姿勢を見せることが、何よりも大切だ。それを念頭に置いておけば、アメリカ側にも交渉をまとめあげたいという力学が働いてくる。共通利益を見出すためには、長期的な視野に立って、アメリカの側の利益を捉える分析的視点が、非常に重要になってくるだろう。
すでに登録済みの方は こちら