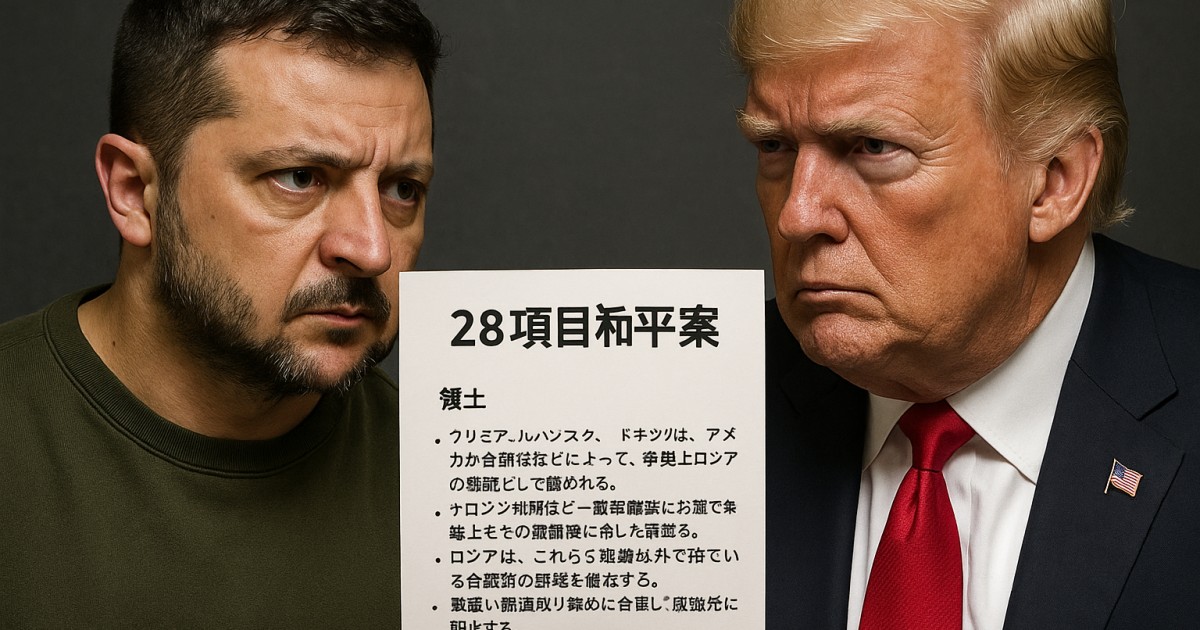BRICS首脳会議、そして中国とインドの確執
BRICS首脳会議における習近平氏の欠席
2025年BRICS首脳会議が、7月6日・7日に、ブラジルのリオ・デジャネイロで開催された。ブラジルがICC(国際刑事裁判所)加入国であることを考慮して、ICCから訴追中のロシアのプーチン大統領が出席を見合わせた(ラブロフ外相が出席)。加えて、中国の習近平国家主席が欠席して、李強首相が出席した。(なおイランのペゼシキアン大統領とエジプトのシシ大統領も中東情勢の緊迫度を理由に結成し、イランからはアラグチ外相、エジプトからはマドブリ首相が出席した。)
この中で、習近平国家主席の欠席は、注目を集めた。BRICS首脳会議の欠席は、2013年の国家主席就任以来、初めてのことだったからだ。BRICSそのものへの軽視とは推測されないため、健康状態に関する憶測も流れているが、政治的な注目点は、中国とインドの関係だろう。4月のジャンムー・カシミールのパハルガムにおけるテロ事件を受けて、5月にインドがパキスタンを攻撃して、両国の間で軍事衝突が発生してから、中国は従来よりもさらに踏み込んでパキスタン寄りの姿勢を示している。バングラデシュを交えた三カ国外相会議を開催するなどして、インドをけん制している。
昨年10月のロシア・カザンで開催されたBRICS首脳会議にあわせて、カシミール中印間の国境係争地帯の警備巡回方法について、習近平国家主席とモディ首相が合意を果たし、関係改善が図られたと見られた。新たなインドとパキスタンの軍事衝突は、その後に発生した事件であった。中国は、あらためてパキスタンの後ろ盾としての立場を確認している状況だ。
インドとパキスタンは、ともに核保有国だと言っても、経済力を基盤にした国力においては、圧倒的な格差がある。人口14億のインドのGDPは、人口2.5億のパキスタンの10倍の規模に達している。一人当たりGDPも、インドはパキスタンの2倍の規模だ。兵力数も、約145万人を擁するインド軍の規模は、約65万人のパキスタン軍の2倍以上の規模だ。パキスタンがインドに対抗するためには、中国の軍事支援やイランなどの他のイスラム諸国の政治的支持が不可欠となる。中国にしてみても、カシミール問題のみならず、南アジアでインドの勢力が拡大しすぎるのは、警戒する立場にある。
BRICS外相会議・SCO国防相会議での共同宣言見送り
4月に開催されていたBRICS外相会議では、共同声明の採択ができなかったことが話題となった。インドとブラジルの国連安全保障理事会常任理事国入りを支持する表現を用いるかどうかをめぐって対立が生じたことが原因だったと報道されている。今回のBRICS首脳会議では、インドとブラジルの国連安保理でのより大きな役割(a greater role)を支持するという表現が用いられたが。常任理事国という表現は回避された。「大きな役割」を期待するが、「常任理事国」入りは具体的には明記しない、という姿勢は、少なくとも習近平氏が国家主席に就任して以来、一貫してBRICSでも踏襲されている立場である。
さらに6月にはSCO(上海協力機構)の国防相会議で共同声明が採択されなかった。インドの複数のメディアは、同国のシン国防相が共同声明への署名を拒否したことが理由だと報じた。インドとパキスタンの軍事衝突への言及があったが、それに先立つパハルガムでのテロ事件への言及がなかったためであったという。このSCO国防相会議の議長国は、中国であった。また、パキスタンは2017年にインドと同時加盟を果たしたSCOの正式メンバー国である。
今回のBRICS首脳会議では、過去2年間続いていたBRICS加盟国・パートナー国の「拡大」に関する決定がなされなかった。加盟申請をしているとされる国の一つがパキスタンだが、BRICSについては、インドが事実上の拒否権を行使しているため、パキスタンの加盟の可能性は限りなく乏しい。今回のBRICS首脳会議の共同声明では、インドとパキスタンの軍事衝突ではなく、パハルガムのテロ事件への非難が挿入され、テロを防ぐための諸国(さすがにパキスタンが名指しはされていないが)の努力の重要性も強調された。
中国が創設国で主導権を持ち、パキスタンも加入しているSCOと、インドが原加盟国でパキスタンが加入していないBRICSとの違いが、鮮明になった形だ。
引き続き「多極化した世界」を目指すBRICS
なおBRICS首脳会議にあわせて、トランプ大統領が「BRICSの反米姿勢に同調する国に10%の追加関税をかける」とSNSで発信したことがニュースになった。またBRICS首脳会議共同声明でも、名指しは避けつつも、アメリカのイラン攻撃への非難の文言が入った(イランはBRICSの正式加盟国)。トランプ大統領の一方的な高関税政策を憂慮する段落もある。イスラエル非難となるガザ危機に対する非難と憂慮の文言も入った(イスラム圏のエジプト、UAE、インドネシアがBRICSの正式加盟国)。なお日本のメディアはさらに、ロシアの民生施設への攻撃に対する非難の文言が入ったが、ウクライナ領への攻撃への言及がないことを強調している(ロシアがBRICS加盟国で、ウクライナはそうではない)。
だがこれらはいずれも、31ページ126段落の共同声明の中の個々の段落の中における言及に過ぎず、全体の基本トーンを決定づけているほどとは言えない。https://brics.br/en/documents/presidency-documents/250705-brics-leaders-declaration-en.pdf/@@download/file
日本のメディアの報道では、BRICSがトランプ大統領の圧力に危機感を覚えて反発、といった見出しが見られるが、脚色のしすぎだろう。BRICSは一貫して、「多極化した世界」を目指しており、それは今回の首脳会議でも踏襲されている基本トーンである。
さらに言えば、BRICSとアメリカの関係だけでなく、中国とインドの間の確執も、BRICSが目指す「多極化した世界」の一環でとらえておくべきだろう。インドのGDPはいよいよ世界第3位の地位を占めるに至り、BRICS内部でも、依然として中国との差は圧倒的だとしても、インドと他の諸国との間の経済力の差も目立ってきている。「多極」は、アメリカとBRICS全体ではなく、アメリカと中国・インド・ロシアなどの有力国との間で形成されるものなので、「二極」ではなく「多極」であることには注意が必要である。
その意味では、中国とインドの間の大国間の確執は、当然、注目すべき点になる一方、それが現時点でBRICSを破綻させたり迷走させたりするほどのものであると考えることは、発想の飛躍である。
この辺りの事情は、7月30日公刊予定の私の拙著『地政学理論で読む多極化する世界:トランプとBRICSの挑戦』を、いずれ参照していただければ幸いである。https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8E%E5%9C%B0%E6%94%BF%E5%AD%A6%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%80%E5%A4%9A%E6%A5%B5%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A8BRICS-%E4%BB%AE-%E3%80%8F-%E7%AF%A0%E7%94%B0%E8%8B%B1%E6%9C%97/dp/4910364854
「篠田英朗 国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月二回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。https://nicochannel.jp/shinodahideaki/
すでに登録済みの方は こちら