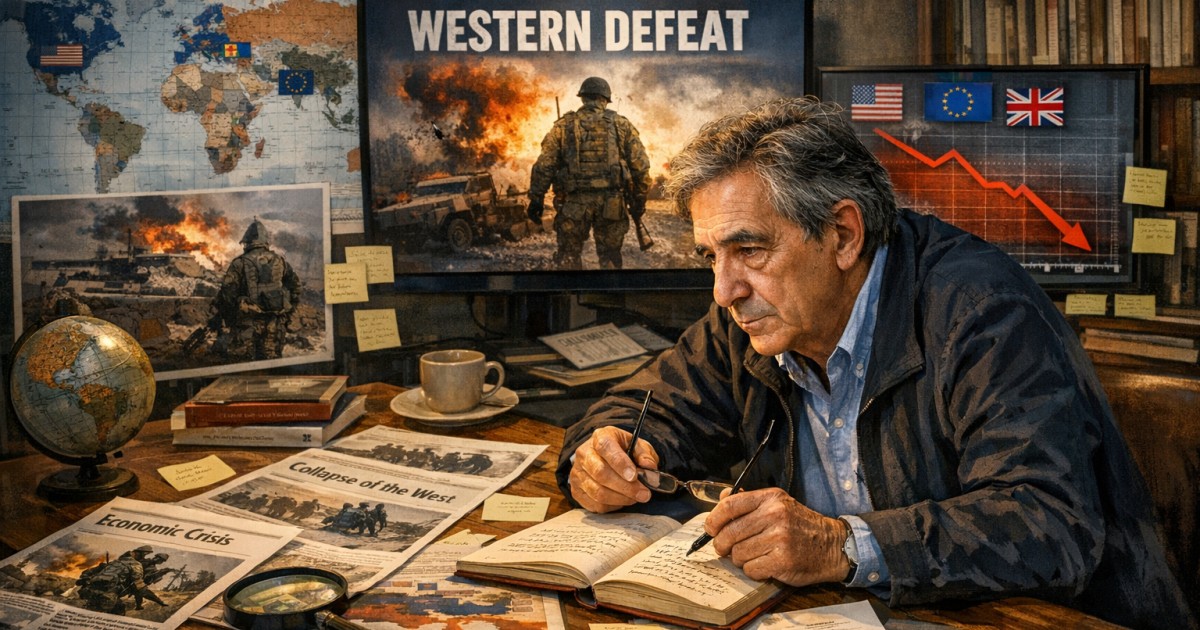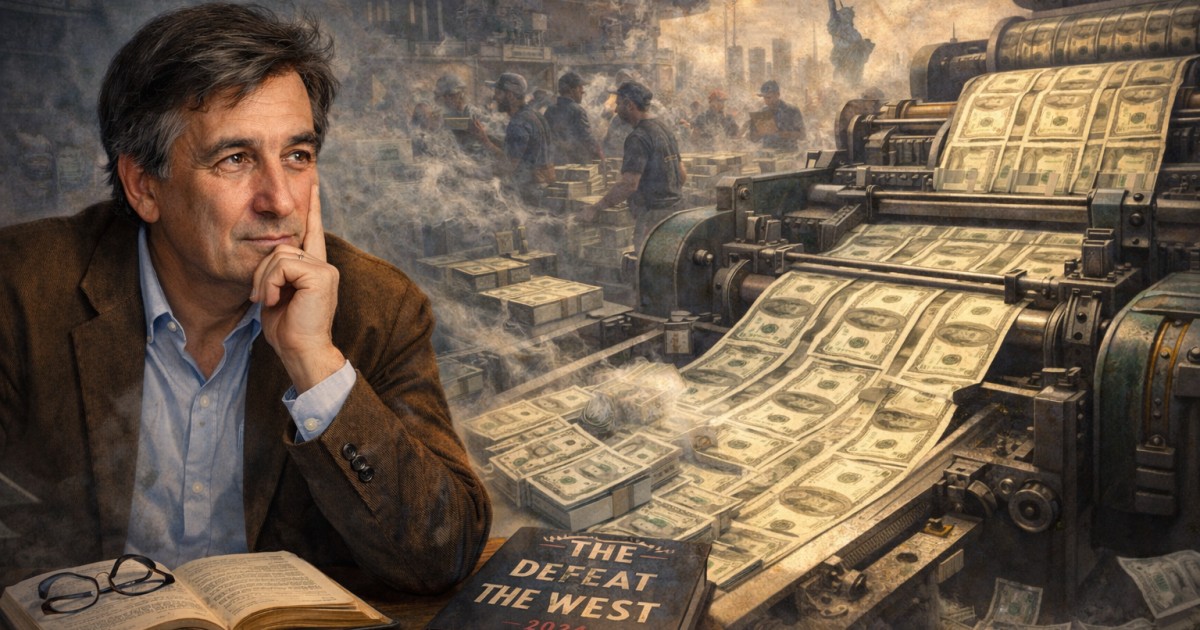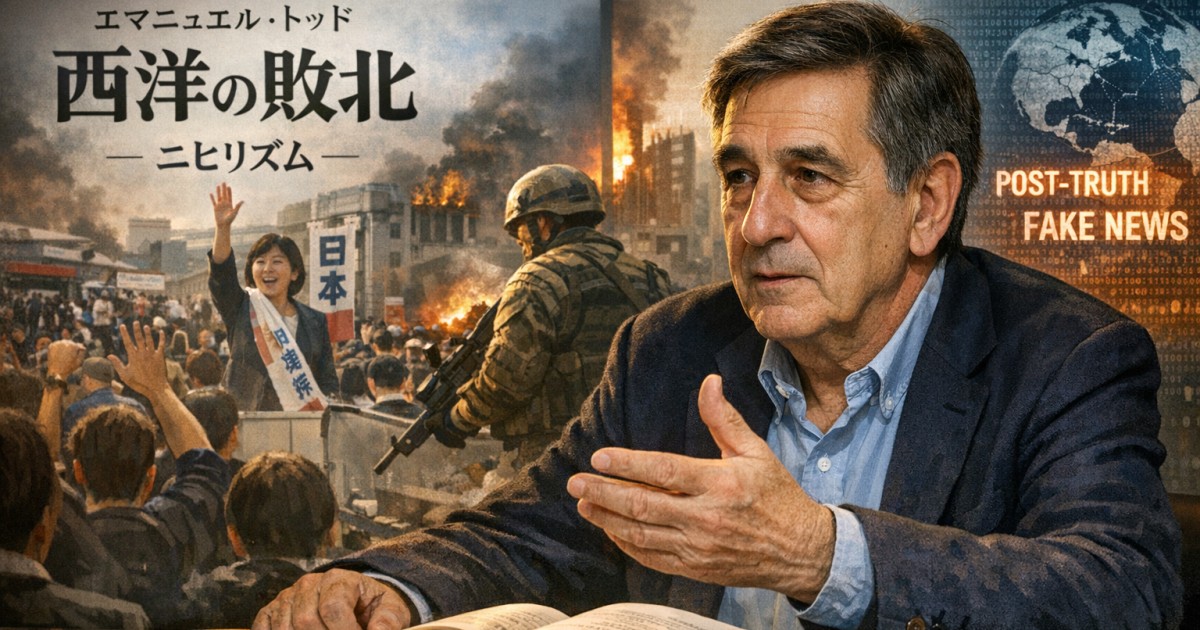アメリカの高率関税の伝統:ハミルトン主義とマッキンリー主義
ハミルトン初代財務長官「製造業に関する報告書」
アメリカの高率関税の歴史は、少なくとも連邦政府初代財務長官アレクサンダー・ハミルトンにさかのぼる。植民地から脱したばかりの合衆国構成諸州では、農業が基幹産業だった。奴隷交易を前提にした大西洋貿易システムの支柱の一つを形成していた合衆国の大規模農園経営者たちは、低率関税を望んだ。これに対して北部知識人層は、欧州列強に対抗できる製造業の育成を政策課題として掲げた。その代表的人物が、ニューヨーク出身のハミルトンだ。
ハミルトンが財務長官時代に議会に提出した「製造業に関する報告書」は、合衆国の歴史の中で大きな影響力を放った文書である。邦訳もされているので、この機会に読んでみた。ハミルトンは、合衆国憲法制定時の『ザ・フェデラリスト・ペーパーズ』の論客としても有名だ。私はこちらには相当前からなじんでおり、彼の論理的議論には、一目置いていた。アメリカには「建国の父(ファウンディング・ファーザーズ)」という言葉があるが、ハミルトンのような天才を革命期に要職に置くことができたのは、その後の合衆国の歴史に計り知れない意味があった。
「製造業に関する報告書」も、極めて精緻な論理が無駄のない筆致で進んでいく。さすがに歴史に残る名報告書と評判の高い書物だ、と感じた。今日の学生の論文指導の用途でもサンプルとして使えそうなものだ。
ハミルトンは、まず合衆国は農業を基盤にしている、という主張を取り上げる。今日から見て興味深いのは、国際的な分業体制の中で、合衆国の相対優位は、大規模農園の経営にあり、欧州諸国に太刀打ちできない製造業に深入りするべきではない、という議論があったことだ。
ハミルトンは、製造業の重要性を過小評価する意見を一通り紹介したうえで、精緻に反論を試みていく。その要点は、製造業の発展なくして、健全な社会の発展はない、という思想である。もし現在の合衆国の製造業が極めて脆弱であるならば、それは国家介入をしてでも製造業を育成しなければならない必要性があることを意味する、と説く。そこでハミルトンが列挙する具体的な製造業育成のための政策の筆頭が、高率関税だ。邦訳書を引用してみよう。
「製造業に関する報告書」と高率関税
「如何なる手段に頼ることが合衆国にとって適切であるかについて一層良い判断を下すためには、他国において採用されて成功した手段について論及することが有用であろう。その主要なものは次の通りである。
一、 保護関税 すなわち、奨励が見論まれている国産品と競合する外国品に賦課される関税。 この類の関税は、明らかに国産製造品に対する実質的な奨励金となるものである。・・・
二、 競合品の輸入禁止あるいはそれに等しい関税。 これは自国の製造業を奨励するためのもう一つの有効な手段である。・・・国内市場をもっぱら自国の製造業者に独占させることが製造業を営む諸国の支配的な政策であることを考えるならば、合衆国の側でも適当と考えられるあらゆる場合にわれわれが同等の政策を採用すべきことは、分配的正義の原則の、そしてまさに、わが市民に利益の互恵性を保証するよう努めるべき義務の命ずるところであるとさえいって良いであろう。
三、 製造業原料の輸出禁止。・・・
(四、奨励金 五、懸賞金)
六、製造業原料の関税免除。・・・新しい製造業にとって当然妨げとなるような困難に加えて、関税の負担という障害を新規製造業に与えることはおよそ賢明とはいい難い。」(『アレクサンダー・ハミルトン製造業に関する報告書』[田島恵児・濵文章・松野尾裕訳][未来社、1990年]、79-89頁。)
ハミルトン主義の伝統の形成
アメリカは19世紀を通じて驚異的な経済成長を遂げた。当時のヨーロッパの政治構造を塗り替えたドイツの経済成長をも上回る圧倒的な発展であった。その牽引車となったのがハミルトンが重要視すべきことを強く主張した製造業であったため、彼の政策課題であった高率関税は、19世紀を通じて、アメリカの国是と言ってもいい重要な位置づけをえた。ハミルトンが、高率関税を通じた競争品目の事実上の輸入禁止が、「分配的正義の原則の、そしてまさに、わが市民に利益の互恵性を保証するよう努めるべき義務の命ずるところである」とまで言っていることには、注目せざるを得ない。
なお1913年まで所得税が導入されていなかったアメリカ合衆国において、関税は連邦政府の活動を支える重要な財源でもあったことも付け加えておくべきだろう。
すでに紹介したように、トランプ大統領も好んで参照する「アメリカン・システム」という概念は、19世紀半ばに確立された高率関税重視の姿勢を中核にする製造業中心主義の経済政策を指す。
ただしこのことは、関税政策をめぐって、論争が全くなかったことを意味しない。むしろ注目政策であったからこそ、具体的な税率をめぐる論争は絶えなかった。常に平均20%以上の関税率を持っていたようなアメリカ合衆国であったが、北部諸州の製造業重視の保護主義者は、さらなる高率関税を望んだ。それに対して奴隷制を前提にした輸出農業が産業基盤の南部諸州は、低率関税を望んだ。この論争が、南北戦争になるまで、決着がつかなかった。逆に言えば、南北戦争とは、南部の分離独立権をめぐる争いであり、奴隷制度をめぐる争いであったと同時に、関税政策をめぐる争いでもあった。すべては密接不可分に結びついていた。
トランプ大統領が、自らの関税政策を説明する際に言及する平均50%の関税率を導入した「マッキンリー関税」で有名なマッキンリー大統領は、南北戦争後の共和党全盛時代を代表する人物である。
トランプ大統領が、「アメリカを再び偉大にする」と主張するとき、「以前に偉大であったアメリカ」のイメージは、19世紀のアメリカであり、マッキンリー関税のアメリカである。高率関税は、そこに政策的というよりも、むしろ思想的あるいは価値規範として、深く入り込んでいる。
マッキンリー主義の高率関税
ただしマッキンリーの時代の高率関税は、より帝国主義的な政策の中で導入された点で、製造業未発達の時代のハミルトンの高率関税論とは少し性格が異なる。現在トランプ大統領は、アメリカ国内の製造業の復活を目指すと述べつつ(ハミルトン主義)、世界の諸国のアメリカが一方的に決めた関税率を受け入れてアメリカの貿易赤字の削減に協力するように強く要請している。この帝国主義的とも形容できる姿勢は、マッキンリー主義であろう。(拙文「トランプ関税で読み直すマルクス主義経済学」https://agora-web.jp/archives/250405113902.html 参照)
現在、トランプ大統領のいわばマッキンリー主義の高率関税の威嚇に、もう一つの超大国・中国は激しく反発して報復関税の導入を宣言している。EUも報復関税を検討しているが、中国よりは柔らかである。残りの諸国は、アメリカとの全面対立は避けたいのが本音であろう。日本は補助金まで導入して、受け入れる構えである。高率関税が、経済学というよりも、政治交渉の道具とみなされていることは、トランプ政権高官がはっきりと述べているところである。
このような思想は、現代の新古典派経済学者には、全く受け入れられないものだろう。だが事実としては、トランプ大統領は、そのような思想を持っているのである。そして、おそらくはトランプ大統領のMAGA政策の強烈な岩盤支持者層も、同じ思想傾向を持っている。私が、トランプ大統領の高率関税政策を、気まぐれの思い付きとみなすことは、大きなリスクがある、と繰り返している理由である。
すでに登録済みの方は こちら