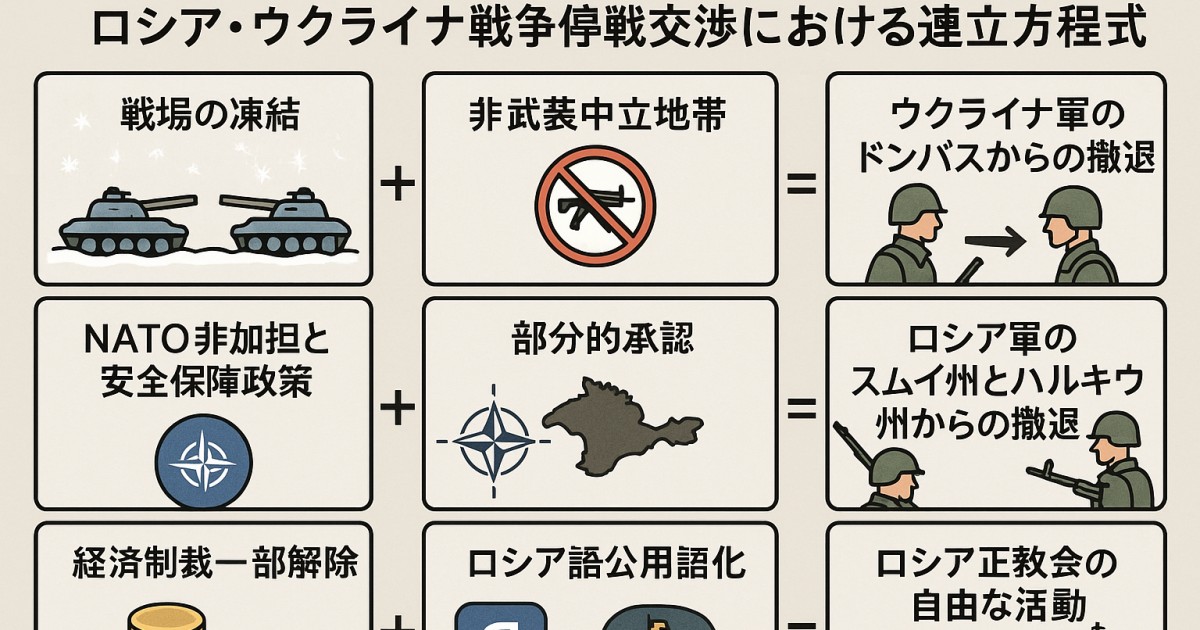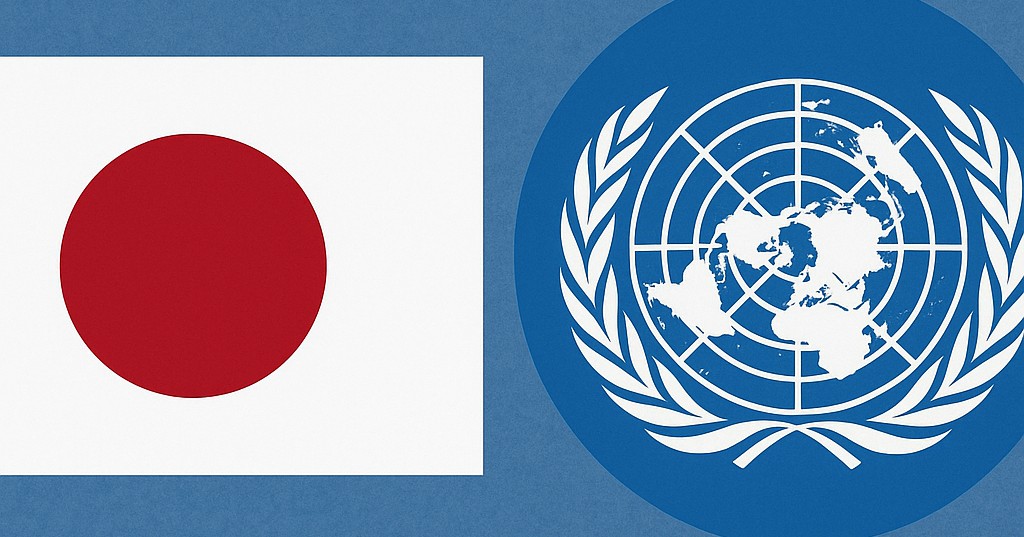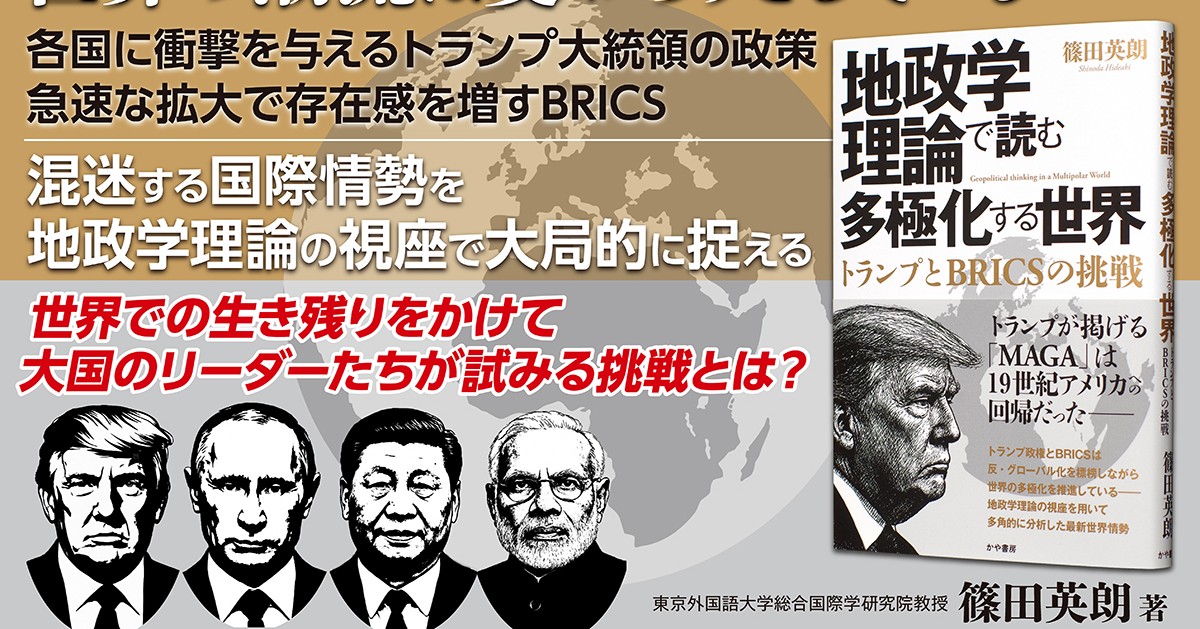アフリカの位置づけ:TICADホームタウン構想の喧騒が語ること
優秀なアフリカの人材
東アフリカの準地域機構であるIGADのLeadership Academyの研修講師として、ケニアにいるところだ。IGADの研修への従事は、7月にも行ったばかりだが、3500人の応募があったという申し込み者の中から、75人を選抜し、25人ずつの研修を三回行っているところである。
折しも日本ではTICADが開催されたばかりだが、開催後に、いわゆるホームタウン構想が、隠れた移民政策ではないか、という指摘で、注目を集めた。移民拡大に反対する人々は、勢い余ってアフリカ人が全体として信用できない人物ばかりだと喧伝しているが、もちろんそんなことはない。Leadership Academyの研修に集まってきている方々は、本当に優秀で、意欲も高い。
アフリカの経済成長の潜在力
アフリカ諸国は人口の拡大を反映して、経済成長を続けている。アジア諸国は人口拡大の峠を越えているが、アフリカは今世紀末まで人口が拡大し続けると予測されている。現在の経済水準は高くないが、人口ボーナスの要素が非常に大きいことが、魅力だ。
もちろん人口拡大に比例して社会的基盤を拡充していくことができるかは、大きな課題だ。教育からインフラに至るまでの全ての領域で、人口拡大にあわせた拡充を図っていくことは、簡単なことではない。
現在においてすでにアフリカ大陸全域で、中国やインドを上回る15億人が存在している。IGADが対象にする東アフリカ8カ国だけで、日本の人口の3倍近い3.3億人がいる。非常に優秀であったり、裕福であったりする階層が確固として存在する一方、教育水準が低かったり、極度の貧困状態にあえぐ階層も存在する。
確かに日本のGDP約4兆ドルに対して、アフリカ大陸全体でもGDPの総計は2.8兆ドル程度だ。日本単独で、アフリカ全体の1.4倍ある。ただし、購買力平価GDPで見てみると、アフリカ全体のGDP(PPP)は約 10兆ドルで、約6.7兆ドルの日本のGDP(PPP)をすでに上回る1.6倍の規模がある。物価水準を加味したGDPで言えば、すでにアフリカのほうが日本よりも明白に大きいのである。
なおアフリカでの一人当たりGDPは、約1,920ドルで、約32,000ドルの日本に遠く及ばない。ただし購買力平価GDPではアフリカは一人当たりで約7,300ドルで、54,000ドルの日本との差は縮まってくる。
この事情に、急速な人口ボーナスが加わる。中国、インドをはじめとする諸国が、アフリカの市場への食い込みに相当な投資をしている理由は、天然資源だけではない。市場=人間の拡大の確実性にも、その理由がある。
この巨大な潜在力を内包しながら、確かになお多くの課題を抱えるアフリカを見て、世界の有力諸国の人々は、一緒に問題解決を図っていきながら相互信頼の関係を強化していこうとしている。日本もそのような諸国の一つであるはずだ。
歪になりがちな日本人のアフリカへの視線
だが、ホームタウン構想の喧騒は、日本のアフリカへの視線が、歪になりがちであることを示唆している。
アフリカ人は野蛮な人ばかりなので、日本に入れてはいけない、といった極論も見られるが、もちろんこれは現実から乖離している。アフリカにも優秀かつ立派な人は、たくさんいる。少なくとも日本人より劣っているという印象は、私は持ったことがない。優秀な人もいれば、確かにそうではない人もいる、と上述した。しかし平均値をとっても、たとえばコミュニケーション能力などに焦点をあててみたら、疑いなく、むしろ圧倒的にアフリカ人のほうが日本人よりも優れていると思う。語学力の彼我の格差は、衝撃的なレベルだと思う。普通の今日行く水準の低いアフリカ人でも、複数の言語を話す。コミュニケーション能力の高さは、アフリカ特有の部族社会の中で、社会混乱の要因になりがちな人間関係の複雑さへとつながっていくこともあるかもしれない。しかしエリート層の国境を越えた人的ネットワークの構築といった言い方をすれば、アフリカ人の能力の高さには、目を見張るものがある。
アフリカの経済水準が低いのは、植民地時代の悪弊の残存や、インフラの未整備、その他の社会的・国際的環境によるところが大きいと思う。克服は簡単ではないが、改善の流れが顕著なところもある。
いずれにせよ、万が一にも、日本人の能力がアフリカ人よりも高いので、現在の一人当たりGDPが日本のほうが大きい、などと誤認してはいけない。
何が重要な施策か
それをよくふまえて、今後の日本とアフリカの関係を考えていくべきだ。私見では、ホームタウン構想が、やや特異な性格を持つものであったことは否めないと思う。日本でのアフリカ人の就労を促進することは、少なくとも普通の意味でのアフリカの開発のための活動ではない。ところがその開発ではない活動が、TICAD(アフリカ開発会議)で語られることの歪さは、どうしても隠しようがない。
この歪さは、TICADが日本が主催国であるという事情と、その日本が深刻な人口減少・少子高齢化の危機に直面しているという事情によって発生しているものだ。決してSNSのデマだけで、歪さが生まれてきているわけではない。移民政策のなし崩し的な推進の問題性は、日本主催のアフリカ開発会議が持つ曖昧さと、密接に結びついている。(TICADについては、別途『フォーサイト』に寄稿した拙稿もご参照ください。)https://www.fsight.jp/articles/-/51586
日本の移民政策については、ここで簡単に結論めいた事項を書けるようなものではない。8月下旬には、広島平和構築人材育成センター(HPC)のスタディ・ツアーで東北の被災地を5日間かけて旅したが、そこであらためて痛感したのは日本の地方部の人口減少の激しさだった。https://x.com/ShinodaHideaki/status/1961432323263795291
一つ確実に言えるのは、日本の国益を考えれば、アフリカの優秀な人材との間の信頼関係の構築の重要性は大きい、ということだ。そして優秀な人材が日本に来ることに躊躇を覚えるようなことがあってはならない。あるいは、優秀なアフリカ人が、まとまった時間を日本でとってもらって貴重な経験をしたと言ってくれるのであれば、その可能性を排斥するのは賢明ではない。
私自身がIGAD Leadership Academyで微力ながら貢献させていただいているのは、研修を通じた参加者との交流だけでなく、研修コースの修了者の間の相互交流の機会の促進であり、そこに私自身も加わることだ。前回7月の修了者たちとの交流も維持しており、オンラインでの会合なども開いている。
日本政府・JICAは奨学金を通じて多数のアフリカ人が日本の大学で学ぶ機会を提供してきたし、研修の機会の提供を通じても多数のアフリカ人を日本に招いてきた。ところが、それらの親日的であるアフリカ人のデータベースは、どこにも存在していない。本来であれば、民間の奨学金団体のように、卒業生の情報管理を怠らず、継続的な交流の機会を持つことを心がけるべきだろう。そうして優秀なアフリカ人との信頼関係の構築を積極的に維持発展させていけば、自然に日本の国益の増進の大きな基盤になるはずである。率直に言って、新たに大きな予算をとって派手な交流目的の新規事業を立ち上げるよりも、意味が大きいはずだ。
ただし、現実には、縦割り行政で2~3年でポストを変えるのが普通の官僚機構がやっている限り、状況は変わらない。私自身の経験を言えば、上記の話をして、反論をしてもらったことがない。しかし日本の官僚機構を動かすのは簡単ではない。卒業生の管理などよりも、新しい予算をとって、次のポストに移ったほうが、官僚の出世にとっては合理的だからだ。
私個人は仕方がないので、それでIGADさんと話をしている次第である。
「篠田英朗 国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月二回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。https://nicochannel.jp/shinodahideaki/
すでに登録済みの方は こちら