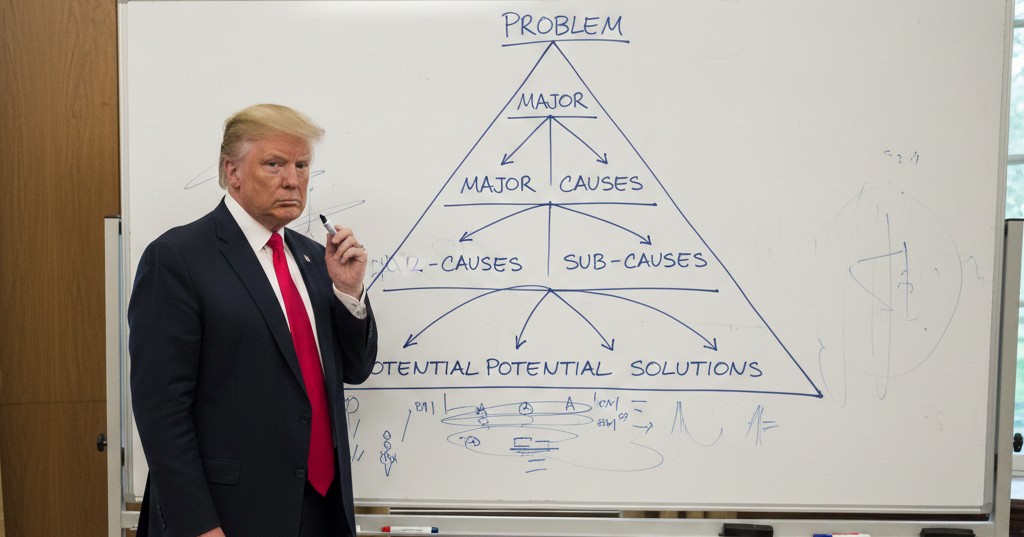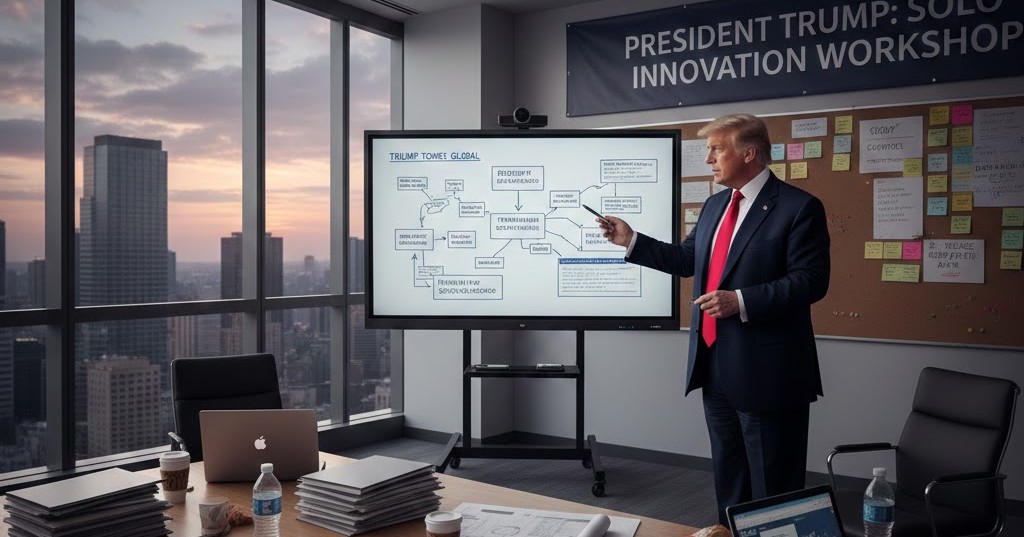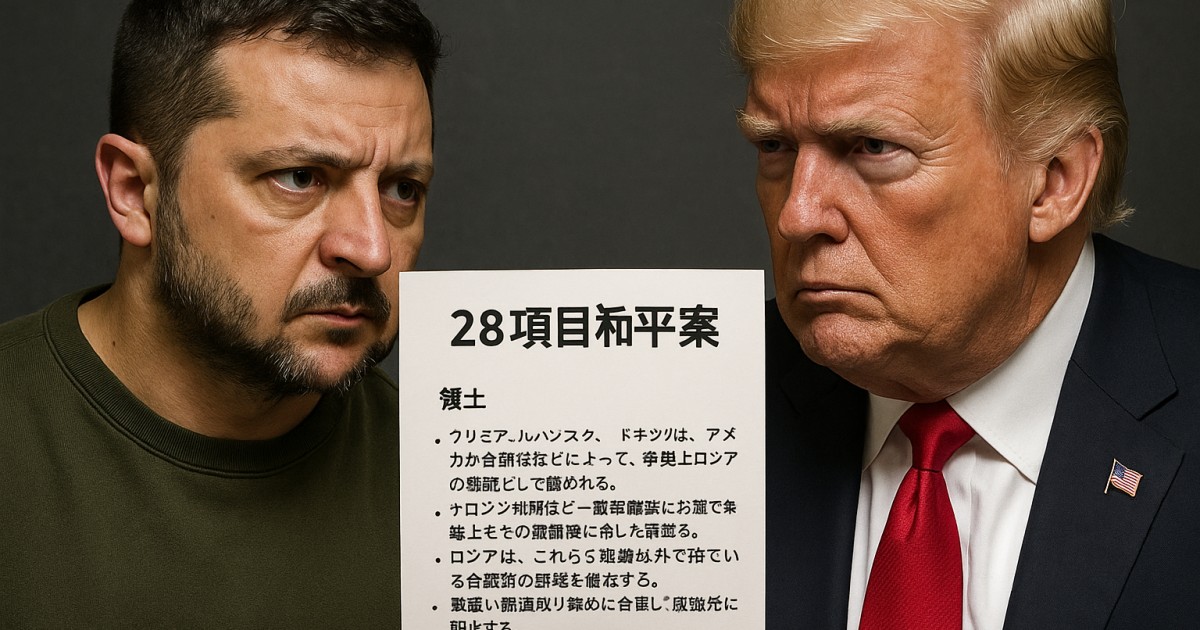野口和彦教授の「予防戦争」論への関心とロシア・ウクライナ戦争
野口和彦・群馬県立女子大学教授が、数日前にXにポストをして、『International Security』誌最新号(Volume 49, Issue 3、Winter 2025)に掲載された論文を紹介した。Barry R. Posenマサチューセッツ工科大学教授の”Putin’s Preventive War: The 2022 Invasion of Ukraine”と題された論文だ。https://x.com/kazzubc/status/1905584641920418162
Posen論文「プーチンの予防戦争」
私もこのPosen論文を読んでみた。一流の研究者が執筆した論文であり、穴がない精緻な議論であった。その論旨は明快で、「ロシアのウクライナ侵攻は『予防戦争』と言える」というものである。「予防戦争」とは、安全保障上の脅威の発生を予防するために起こす戦争、という意味である。ロシアのウクライナ侵攻のレベルで言えば、ウクライナへのNATO拡大を予防するために、プーチン大統領は戦争を開始する決断をした、ということである。
Posen論文は、「予防戦争と言える」と主張できる理由として、ウクライナへのNATO拡大をプーチン大統領が深刻な脅威と受け止めていたと言えること、拡大が近未来の現実的な可能性だとプーチン大統領が捉えていた形跡があること、をあげる。いずれも十二分な歴史的事例及び各国政府関係者の発言を参照して示しているので、説得力がある。
また、Posen論文は、想定される批判的見解として、プーチン大統領は帝国主義的野心を持っているだけで、NATO拡大は戦争原因ではない、という主張については、その議論の限界を指摘すると同時に、イデオロギー的事情は単に「予防戦争」の性格と併存しうる、と論じて、一蹴している。
私見では、Posen論文における論争点は、ドンバス戦争の取り扱いであろうと思う。ロシアの侵略が2014年から始まったと考えるのか、2022年から始まったと考えるのかで、議論の内容は変わってくる。私自身は「国内紛争と国際紛争の不分離性」の理論的観点も加味して、段階論的に言うのを常としている。「予防戦争」論それ自体の論旨は変わらないと思わるが、かなり多くの参照対象の資料の取り扱いや位置づけは変わってくるところがあるとは思う。
この記事は無料で続きを読めます
- 野口教授の「予防戦争」論へのこだわり
- ミアシャイマー教授の位置づけ
- その1:戦争原因論は合法性/正当性の議論とは別の事柄である。
- その2「予防戦争」論が単一理由であるかは不明であり、解釈も確定できない
- その3NATO東方拡大一般ではなくウクライナ加盟問題が争点
すでに登録された方はこちら