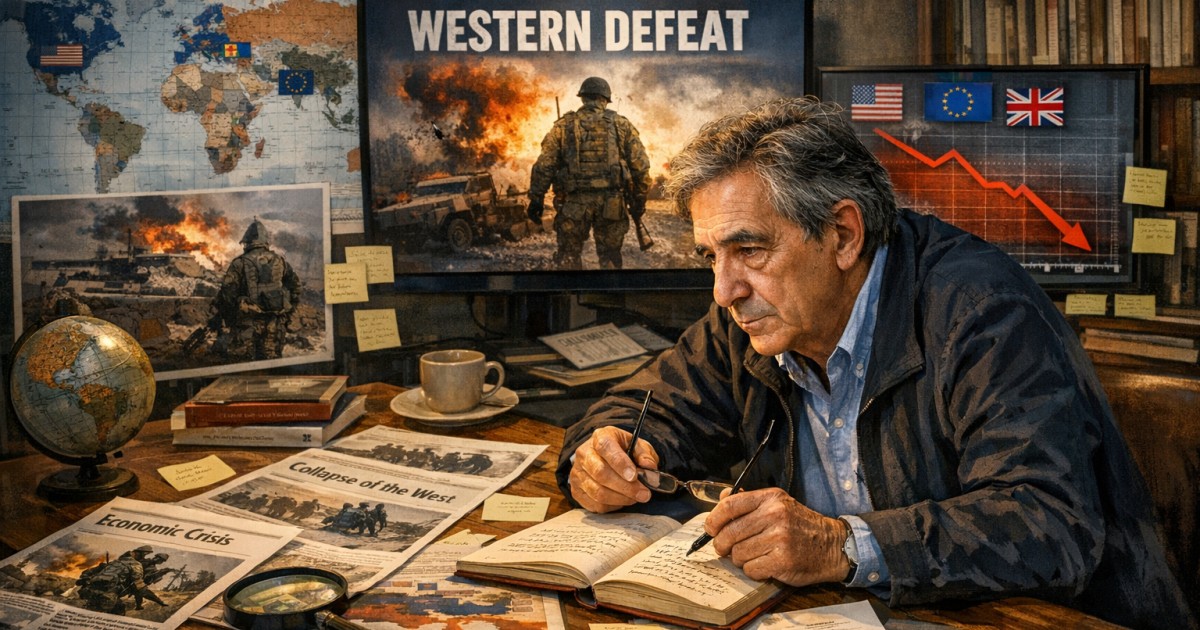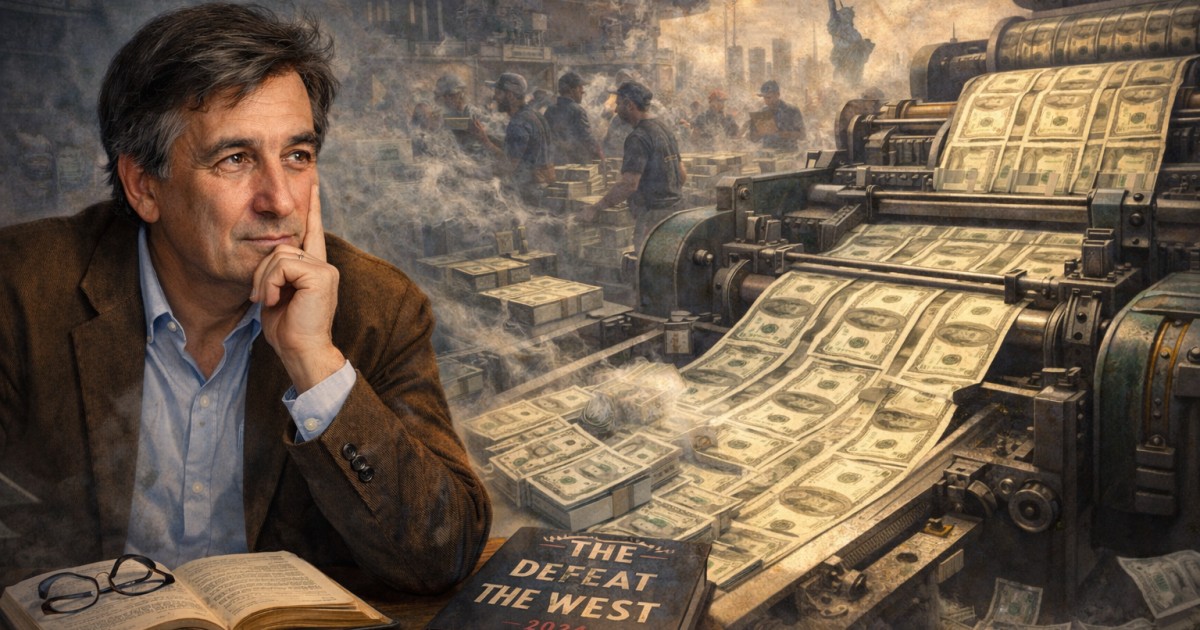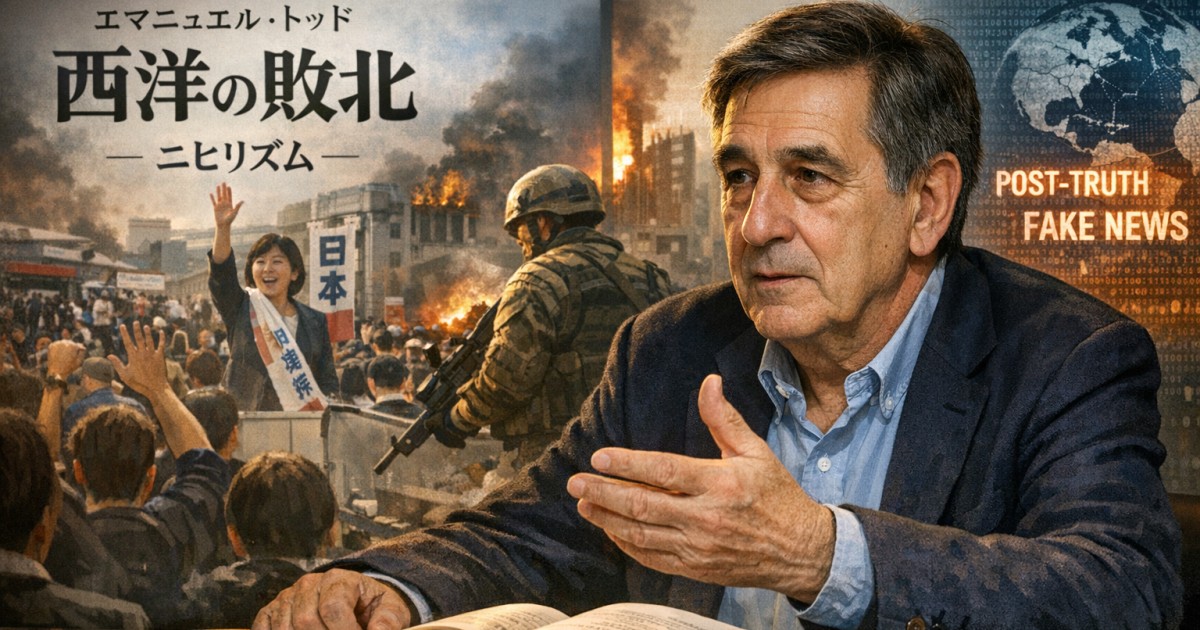トランプ関税と「アメリカン・システム」高率関税の伝統
「アメリカン・システム」と呼ばれた19世紀アメリカの経済体制
「トランプ関税」の導入で触発された私は、何冊もの本を図書館から借り出した。進行中の主専門の仕事もあるため、全て一気には読めないが、それでも色々な仕事と絡めながら読んでいこうと思っている。借り出した本の一冊は、フリードリッヒ・リスト『アメリカ経済学綱要』(1925年)だ。
ドイツ「国民経済学」者として有名なフリードリヒ・リストは、オーストリア宰相メッテルニヒから睨まれて、アメリカに亡命していた時代がある。リストは1789年生まれなので、亡命していた1825~1832年は、30歳台後半から40歳台になったところで、学者としての自分の学説的立場を確立した時期だったと言える。亡命中のリストが執筆した著作『アメリカ経済学綱要(Outline of American Political Economy)』(1827年)は、後の主著『政治経済学の国民的体系(Das nationale System der politischen Oekonomie)』(1835年)につながる着想が書き連ねられている興味深い書だ。
1825年の『アメリカ経済学綱要』で、リストはアメリカの経済システムを「アメリカン・システム」と呼び、肯定的に捉えている。リストが「アメリカン・システム」と呼んだ経済システムは、高率の関税でイギリスの工業製品などがアメリカの市場に入ってくるのを防ぎつつ、税制や補助金を通じた政府の介入的政策で、国内製造業を育成しようとする政策体系のことであった。
前回の「The Letter」記事で書いたとおり、これは初代財務長官アレクサンダー・ハミルトンが議会提出報告書『製造業に関する報告書』で謳いあげた政策体系そのものであった。アメリカは、保護主義の政策を、米英戦争後のイギリスの工業製品の流入をめぐる対応策の検討などをへながら、度重なる関税論争として、意識的に行い続けていたのである。
1824年H・クレイは「『純アメリカ的政策』の採用」と呼ばれる有名な議会演説を行い、国内市場中心の政策を提唱して高率関税の必要性を主張した。1828年にD・レイモンドが「The American System」という匿名論文を書いているが、クレイの主張を裏書きするものであった。一般には1824年クレイ演説が「アメリカン・システム」という用語の起源だとみなされているようである。ただしその政策論の起源がハミルトンの『製造業に関する報告書』にあることは間違いなく、用語もハミルトンが(連邦制度全般について述べた個所ではあるが)『ザ・フェデラリスト・ペーパーズ』で「one great American system」と書いた記述に淵源があるという説もあるらしい。「アメリカの保護主義運動の高揚期」であった1820年代に活躍した「アメリカ体制の最も熱烈な唱道者」の一人とされるH・C・ケアリーは、自らを「ハミルトン経済学派」と呼んでいた。(宮野啓二『アメリカ国民経済の成立』[お茶の水書房、1971年]49、163頁。)
北部州が保護主義で南部州が低率関税主義
当初から南部農業州の利益を代弁する政治家層は、ハミルトンの製造業強化中心政策に、敵対的であった。ニューヨーク州出身のハミルトンは、合衆国憲法制定時には「フェデラリスト」として共同戦線をとった南部ヴァージニア州出身のジェイムズ・マジソンらとも、関税政策などをめぐって対立することを辞さなかった。
当時のアメリカの農業は、奴隷輸入と欧州向け輸出に依存する大西洋貿易システムの中に組み込まれたものだったので、南部諸州は、ハミルトンの高率関税政策にも批判的だったのである。この対立は、結局、1860年代まで持ち越されて南北戦争によって決着をつける構造的なものであった。
しかし逆に言えば、建国時から北部諸州の意向をくんだ保護主義的政策は、連邦政府が推進する経済政策の中に深く入り込む思想となっていた。ジェイムズ・モンロー大統領の「モンロー氏の宣言」が出て、アメリカの「モンロー・ドクトリン」の外交政策が確立され始めていくのは、1823年だった。アレクシ・ド・トクヴィルが一世を風靡する『アメリカのデモクラシー』を公刊するためのアメリカ旅行を行ったのは1831年である。リストが『アメリカ経済学綱要』を公刊した1825年当時は、ヨーロッパ人も着目する新しいアメリカの独自の政治経済システムが確立されようとしていた時期だった。
自由と独立のための高率関税の保護主義政策
前述のH・C・ケアリーによれば、「アメリカ体制」は、保護主義を標榜するにもかかわらず、世界各国民が「人間の自由と国民的独立」を達成するための体制のことであると説明した。それは「国内商業の拡大と社会的循環を刺激するような職業の多様化」を意味しており、「自由・平和・調和への唯一の道」なのだと主張した。イギリスの「自由貿易」が「独占」を維持するための政策であるのに対して、「アメリカ体制」は「独占を打破り、完全な自由貿易を確立する」。(宮野、前掲書、292-3頁。)
「アメリカン・システム」という用語は、一般には19世紀半ばから顕著になったアメリカ製造業の「大量生産」方式を指して使われることもある。独特の工場経営の仕組みなど工業生産の技術的側面に着目した言い方で、意味していることは微妙に違うが、同じ事柄を、後代の人々が、より技術的側面を強調しただけ、ともいえる。アメリカの大量生産方式に裏付けられた製造業を生み出したのは、18世紀の初代財務長官ハミルトンが『製造業に関する報告書』で提唱した考え方を基盤にした高率関税を含む経済政策であったし、それに興味を抱いて後にドイツ「国民経済学」を発展させる着想としたのがリストであった。
いずれにせよ、アメリカには、保護主義の「アメリカン・システム」の経済思想が、歴史的に根深く存在している。「保守主義」者が、中国商品に席巻されたアメリカの製造業を保護して育成するために、高率関税に訴えようとするのは、その意味では、必ずしも驚くべきことではない。
アメリカが自由貿易主義者になったのは冷戦勃発時
アメリカの関税は、第二次世界大戦後にGATT体制を導入するまでは、一貫して今日では考えられないような高率が維持されていた。マッキンリー関税などの措置は、20%以上の関税率が当然だった時代に、さらに平均50%にした時代の話である。今日とはレベルが違う。
一般に高率関税は世界恐慌と結びつけらえることが多いが、アメリカは世界恐慌勃発時まで、歴史的にあり得ない程度にまで関税を下げ続けていた。低率関税の時期に世界恐慌がアメリカ発で勃発し、その後に大国が一斉に高率関税政策に切り替えてブロック経済が進んだことが、枢軸国ドイツや日本の不満につながり、第二次世界大戦が勃発した、というのが史実である。
世界恐慌勃発後に、関税を引き上げた1930年「スムート=ホーリー関税法」が、現代の経済学者の間では、かえって世界恐慌を悪化させた、ということになっているので、あたかも高率関税が世界恐慌につながるかのように考えられているが、それは少なくとも世界恐慌の勃発に関しては、必ずしも正確ではない。

1947年にGATT体制が導入されたとき、アメリカがその主導者であったことから、20世紀後半以降にアメリカは自由貿易主義の指導者というイメージが確立された。アメリカの有名大学で次々と経済学部が設立され、そこでは新古典派経済学に基づく経済理論が主流となった。しかしそれは「自由主義」陣営が、護送船団方式で、共産主義諸国と対決していた、冷戦の時代背景と切り離しては理解できないだろう。冷戦が終わって30年。アメリカの大統領が、自由貿易主義の限界に気づき、自由貿易主義の旗振り役をやめたくなったとしたら、そういう時代の流れもありうる、と考えざるをえない。今や共産党の一党独裁が続く中国のほうが、購買力平価GDPでアメリカよりも大きく、アメリカに巨額の貿易赤字を作り出させているのだ。
日本の識者の間では「トランプがバカだからバカな政策を導入しているが、やがてアメリカの有権者がトランプがバカであることに気づいてバカな政策をやめさせてくれるだろう」という「トランプはバカだ、ただそれだけだ」理論が、主流である。
だがアメリカの政治経済思想に根深く浸透している「モンロー・ドクトリン」=「アメリカン・システム」の思想を考えてみるならば、話はそこまで簡単ではないような気もしてくれる。
すでに登録済みの方は こちら